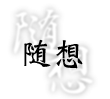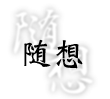| 第29回国民文化祭・あきた2014の事業のひとつとして、先月(10月)4日、「全国ナマハゲの祭典」が男鹿市民文化会館で開催された。ステージ上でナマハゲに類似した各地の来訪神行事が再現されたほか、「男鹿を愛した菅江真澄とナマハゲ」というタイトルで女優の浅利香津代による朗読のパフォーマンスも行われた。筆者がこの朗読の脚本を担当したのだが、そのストーリーの主軸に据えたのが、菅江真澄が描いたナマハゲの絵であった。ここに掲載しているのがその絵で、ナマハゲの実見記録では最も古いものとされる。
文化8年(1811年)、1月15日の夜、今の男鹿市宮沢に滞在していた菅江真澄が見たナマハゲの姿は、現在の様子とちょっと違っている。向かって右の赤鬼は、小さな箱を腰のあたりにつけている。真澄は中で何かがころころと鳴っていると書いているのだが、何が入っているのかよくわかっていない。
左のナマハゲは頭に赤い鉢巻きのようなものを巻いて、真澄が空吹の面と書いているお面をかぶっている。空吹というのは、能や狂言で使われるお面で、うそ(空)とは古いことばで口笛のこと。つまり、口笛を吹くように口をとんがらしたひょっとこ面のことをいう。
赤鬼の腰につけた箱にしろ、ひょっとこのお面にしろ、どちらも今では見られないナマハゲの姿である。真澄が記録してくれたおかげで、私たちはおよそ200年前のナマハゲ行事の様子を、こうして知ることができるのである。
菅江真澄が生まれたのは宝暦4年(1754年)、今からちょうど260年前のこと。30歳のころに故郷の三河の国、今の愛知県を離れて北の国をめざす旅に出たのだが、その旅の目的はよくわかっていない。福島を除いた今の東北5県のほか、当時の蝦夷地、北海道にも渡っている。
40代後半からは秋田領にとどまり、亡くなるまで30年近い長きにわたって秋田の各地をめぐった。なかでも男鹿は少なくとも4回訪れ、その旅の記録は『男鹿の秋風』『男鹿の春風』『男鹿の鈴風』『男鹿の島風』『男鹿の寒風』と題した5冊の旅日記にまとめられた。どれも「男鹿の〜風」という題がついているので、民俗学者の柳田国男が5冊まとめて「男鹿五風」と名付け、以来、真澄の男鹿紀行はこの名で呼ばれるようになったのである。
ナマハゲの記録が載っているのは「男鹿五風」のひとつ『男鹿の寒風』で、絵には次のような説明文が付されている。
「正月十五日の夜遅く、若い男たちが集まり、鬼の仮面や可笑という空吹の面、木の皮を赤く塗った面をつけ、螻蓑というものに、海菅という黒く染めた海草を身にまとって振り乱す。手には小刀を持ち、中にころころと鳴るものを入れた小箱を脇に着けて、肩を怒らし、蒲の脛巾(蒲の葉を編んでつくった脚の脛当て)、海菅の脛巾に雪沓を履いて、家に突然入ってくる。すると、”ああおっかね、ナマハ |
 |
ギが来た!”といって、子どもは声を立てることも出来ず、あわてて逃げ隠れるのである」(現代語訳)
絵をよく見てみよう。家の人がいるのは居間で、餅を持っているのはご主人、衝立の陰に隠れているのはその奥さんだろうか。奥さんに抱かれている子どもは女の子、布をかぶっているのは男の子のようだ。ご主人も奥さんも家の中でも被り物をしているが、真冬の季節なので土間の戸を開け放すと寒いからであろう。
絵を見る限り、主人は戸板に身体を半分隠して立ったまま餅を差し出しているので、このころのナマハゲは座敷にあがってこなかったようだ。今なら今年の作柄についてナマハゲと問答をしたり、「ナマハゲさん、よぐ来てけだしな」といって酒をついでもてなすのが普通なので、ナマハゲに敬意を払っていないようにも見えるが、実はその反対で、ナマハゲに対する畏敬の念が今以上に強かったので、このようにおそるおそる餅を差し出しているとも考えられる。
それにしても不思議なのは赤鬼が腰に付けている箱である。ひょっとこのお面をかぶっているほうも、腰に「こだし」のようなかごを下げている。何か入れるためのものなのか、それともただの飾りなのか、200年前のナマハゲに聞いてみないことには、今となっては確かめようがない。
主人の持っている餅は丸や四角いきれいな餅ではなく、形がいびつなのも注目したい。神様に供えるものには刃物を使わないのが原則である。餅を手でちぎったので、絵のような形の餅になったとすれば、このころからナマハゲは神様、あるいは神様の使いとして男鹿の人びとに理解されていたのだろう。
また、真澄はナマハゲが「わぁ!と叫び声をあげて入って来た」と書いているだけなので、今のように「なぐ子はいねが〜」「あぐだいる子はいねが〜」「怠け者はいねが〜」「こごの家の嫁は早起ぎするが〜」などの文句で脅すことはしなかったようだ。ただ、そうして威嚇しなくても、子どもや女性にとって恐ろしい存在であったことは、この絵から十分伝わってくる。
このナマハゲ行事を記録した文化8年の正月で、およそ1年にわたった男鹿の旅は終わりを告げ、これ以降、真澄は久保田城下、今の秋田市中心部に住むようになる。久保田では秋田藩の藩士と交流を深め、そのとりはからいで9代秋田藩主・佐竹義和から、秋田六郡の地誌編纂を依頼される。本格的に執筆にとりかったのはすでに70歳を過ぎたころであったが、平鹿郡全14巻を完成し、さらに仙北郡25巻の完成間近というところで、旅先の仙北で76歳の生涯を閉じた。
真澄は男鹿のすべての日記になぜ「風」と名付けたのだろうか。ナマハゲのいるという「おやま(真山・本山)」から吹き下ろす寒風。息ができないほど吹きつける海からの潮風。里山の春の桜を散らすそよ風。ハタハタを呼び込む冬の初めの季節風。いつも被っていたという頭巾の裾をそんな風になびかせた菅江真澄が、確かな足どりで今も男鹿のあちこちを歩いているような気がする。 |