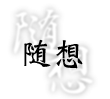
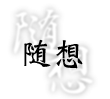 |
|
| カレント・トピックス | 菅 禮子(作家) |
| 幼い頃、ラジオ放送で、よく“カレント・トピックス”というのを耳にした。「○○は○銭なり……○○は○銭なり 今日のトピックスは……」という株価の高下についての中の語彙であったので、成人するまで株の特殊用語だと思っていた。 近頃、ふと気になって辞書で調べてみたら、“時の話題”あるいは“時事問題”となっている。 今さらに己の無知を思い知ったが、ひるがえって考えてみると、“株”という語彙が今日ほどカレント・トピックスになっている時代はないのではないか― 今は昔とちがってテレビ時代になったが、夜のニュース番組のあとに、必らずその日の国内外の株価が画面に紹介される。 「ロンドンでは1円下がって○○円」などと… その中で国際通貨と国内の株価のつながりがよくわからない。そこでこの面に詳しいTさんに「株価ってどうやって決まるの」と教えを乞うてみた。 するとTさんは言下にこう言ったのだ。「およしなさい。射倖心というのは身を滅します!」 “射倖心”?これも辞書をひいてみると“偶然に儲けようとすること。―下心” 別に私は、株の知識を得て儲けようという下心があったわけではない。全くの知的関心からである。当時私は『原点』という“文化誌”の編集に携わっていた上に、もともと経済学というのが好きだった。今でこそ出身校は大学という名称がついているものの私の時代は明けても暮れても勤労動員と称する軍事生産のための勤労奉仕に携わっていたから、一般教養というものが悲しいことに身についていない。しかもこの「株」の世界については全く無知。子供の頃からなんとなく近づいてはいけないヤバイ世界という観念がしみこんでいた。 しかし公共放送で堂々と報道するところから考えるとこれはやはり、一般教養知識として、その仕組みをのみこんでおく必要があると思ったのである。だからTさんの言う「株の学習イコール射倖心」という図式がよくわからない。しかもご本人は株の売り買いに傾倒していた。戦後1ドル360円で出発した日本の円が1ドル145円になった時がある。 そのときTさんは言った。 「円が140円代になると大へんです」「そうなるとどうなりますか?」と訊くと「日本は亡びるでしょう」 けれども1ドル145円になっても日本は亡びなかった。 これはいったいどういうことなのか? 今から数十年前の話だがたまたま某放送局の番組審議委員になったことがあって、その席上「この国際通貨のしくみというか、株価というものについて女性が勉強する教室を設けてほしい」と希望をのべたところ、臨席していた当時の副局長が烈火のごとく怒り出したのである。彼はわめいた。 「とんでもない!そんなことをしたら局の存在にかかわる。」 すると当時の局長が、かれを制して「実は、そういう国際経済についての教室というか講座はすでに設けてあります……」 |
未だに私はなぜ副局長が怒り出したのか、わからないでいる。やはりTさんと同じような射倖心として受けとったとしたら、人をバカにするな!と言ってやりたい。その時、言えなかったのが今もってくやしい! ただ、もしその時その講座で(どんなことを教えていたかわからないが)“マネーロンダリング”とか“マネーサプライズ”とか、今、かまびすしいそれこそカレント・トピックスの「株」にまつわる問題を教えてくれていたら、今ほどチンプンカンプンではなかったろう。 マルクスやアダムスミスの理論は一般常識としてわかっていても、この世界の「専門用語」は案外わからない人が多かったのではないか?今さらになってテレビ番組でいろいろな事例を出しながら教えている(私は辞書をひいて知ったが)……。特に興味それこそ射倖心でもって、この世界に関心を抱いている人々のほかには…。 そしてまた射倖心即ち悪とは私は思っていない。その人その人の幸福の追求の仕方なのだから―。それこそ儲けるのも大損するのも自由であろう。 もう一つわからないことがある。私はゲームが好きだ。あらゆるスポーツ、トランプ、オセロ、将棋、それもいつも負けてばかりいるから下手のナントカというのであろう。 しかし、男の人に「トランプしましょう」というと「いくら賭ける?」という答えが返ってくる。「別に…カケごとじゃないんだから」というと「じゃおもしろくない」 男の人というのは、どうして、こうなのだろう。 いや、そうでない人もいる。韓流映画「オールイン」の主人公のモデルになった男性である。彼は大勝負をやって大金を手にするが私が彼を好きなのはまったくというほど射倖心というのがないからだ。彼をつき動かしているのは、ひたすらギャンブルに対する情熱、言いかえれば知的興味であり、ひいては自分のために傷つき、悲惨なめにあった人に報いたい、幸せにしたい―。彼のすべての原点はそこに凝縮しているからである。 これはモデルの実話にいくらかフィクションも加味しているだろうが、こういう男の生きざまを描き出した制作者の心・志操に敬意を表したい。 ”木を見て森を見ず“という詞があるがTさんも先の副局長も、その傾向がありはしないか―先の、ライブドアのホリエモン氏。日本人の射倖心の堂々たる旗頭だが国会でこの時とばかり政府を責めつづけた野党も、マスコミもそして与党も皆、なにか大切なものを見落してはいないか、そんな気がしてならない。 ”オールイン“の主人公のように義と愛と友情にみちた(それは古来、日本人の固有の美徳であった)人づくり、大人も子供もすべてをかかえた社会づくりによる心のルネサンスを考え、実行し、またそういう選良を世に送り出すべきだと、私は思うがどうだろうか。 |
![]()